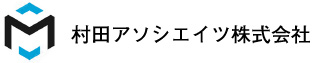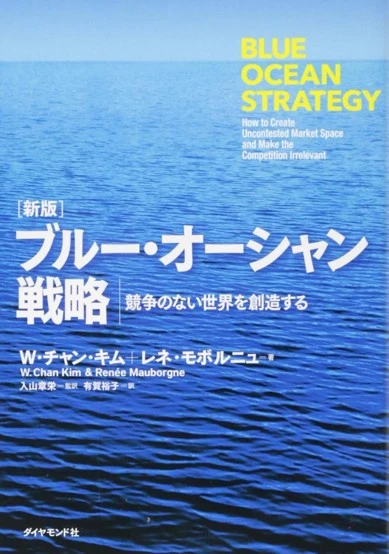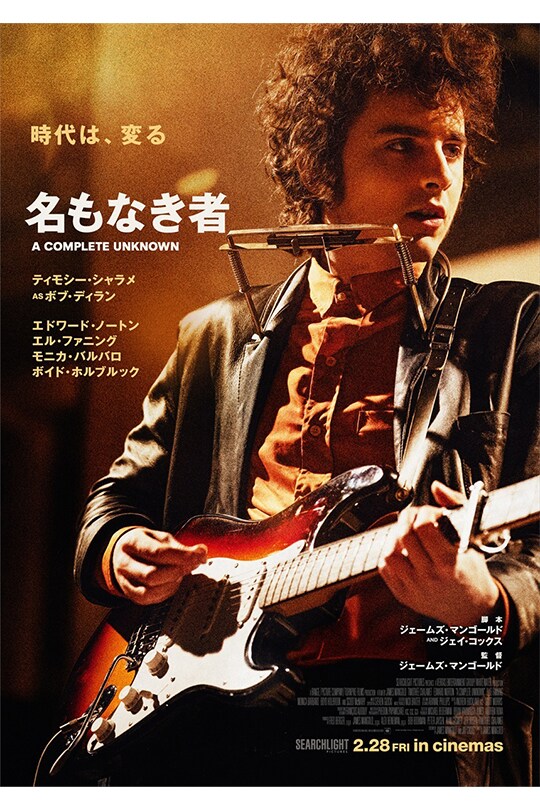高齢者住宅新聞連載 村田裕之の「シニアビジネス相談室」第92回
皆に『やめておけ』と言われる事業をやるだけでは成功しない
前回、大勢の人に「やめておけ」と言われる事業は狙い目だと言いました。こう言うと、「じゃあ、大勢の人に『やめておけ』と言われる事業をすれば成功するのか」と思うかもしれませんが、それだけでは成功しません。
女性専用フィットネス・カーブスの成功要因の一つは、2005年当時日本にまだ存在しなかった「30分サーキットトレーニング」というカテゴリーで事業を行い、他社に先んじて店舗展開を図ったことです。いわゆる「ブルー・オーシャン(青い海)」戦略を取ったのです。
これは、従来存在しなかった新しい領域に事業を展開し、新市場を創出する戦略です。この考えは、欧州のビジネススクールINSEAD教授のW・チャン・キムとレネ・モボルニュによって提唱されたものです。
ブルー・オーシャン戦略で店舗数を伸ばした最近の例では、㈱RIZAPの小型ジム「チョコザップ」、㈱nobitelのストレッチ専門店「ドクターストレッチ」などが挙げられます。どちらもそれまでにない新たな事業領域です。シニア向けとは謳っていませんが、中高年利用者は多いです。
既存市場への参入で差異化できないならブルー・オーシャンを見つけよ
一方、ブルー・オーシャンと対立する概念が、「レッド・オーシャン(赤い海)」です。これは、多数の競合企業と争う既存の事業領域のことを言います。
ここでは、限られたパイを奪い合うため競争が激しく、競合との血みどろの戦いが不可避です。また、レッド・オーシャンでは、商材価値が一般化するコモディティ化も進みやすく、継続的に収益を上げることが難しくなります。
私は多くの企業から新規事業の相談を受けます。当該事業が苦戦している場合、調べてみるとレッド・オーシャンで戦っていることがよくあります。
既に多くの競合企業がひしめいている中で、新規参入して事業を伸ばすには、相当の差異化が必要です。それにも関わらず、差異化が弱い例がしばしば見られます。
こういうミスを犯すのは、企業の担当者が、自社の事業の「ブルー・オーシャン度」を事業開始前に十分に認識できていないことが原因です。