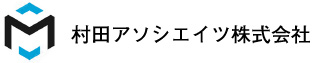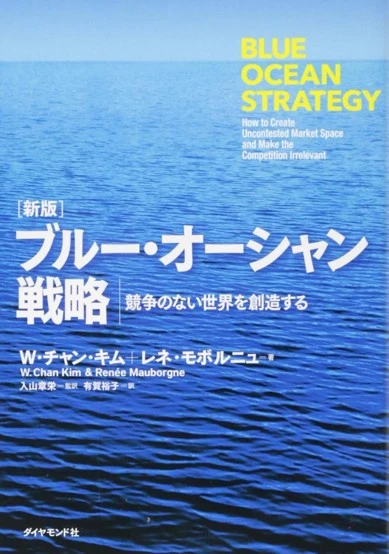シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第215回
「ちかく」のグループ通話機能とは?
本連載第205回で取り上げたデジタル近居サービス「ちかく」にグループ通話機能が実装された。これは、1人暮らしの高齢者が自宅のテレビの大画面で、複数の家族や親戚などと顔を見ながら会話できるものだ。
従来モデルでは、離れて一人で暮らす親が、使い慣れたテレビで子供と1対1で会話ができた。
新モデルでは、例えば、鹿児島に一人で暮らす母が、東京に住む長女、北海道に住む次女、米国ロスアンゼルスに住む孫娘の3人と、母宅のテレビ画面に一堂に会して会話できる(写真参照)。
電話・スマホでの会話では不可能なことが可能になる
新モデルの可能性を述べる前に、従来モデルがどう使われているかを整理したい。一つ目は、離れて暮らす親の服薬管理だ。
神奈川県の佐藤正子さん(仮名、55歳)は、「新潟に住む父が10種類くらい薬を飲んでおり、飲み忘れが多いので、朝晩、服薬したかどうかを画面越しで確認できて、助かっている」と言う。
薬飲んだ?の会話はもちろん、父の部屋にあるお薬カレンダーが画面越しに見えて助かるとのことだ。
二つ目は、日常生活の細かなサポート。静岡県の木村幸子さん(仮名、60歳)は、「新しく買い替えた家電の使い方を教えたり、郵便物の中身を一緒に確認したり、離れて住む親の生活サポートに役立っている」と言う。
福岡県の田中光代さん(仮名、63歳)は、「自分とテレビ電話で話しながら冷蔵庫を確認させ、足りないものがあれば聞き、それを親宅に近居する兄に伝え、兄が食材を補給している」と言う。
親が認知症の方では、次の日のデイサービスの手荷物 (お風呂セット、下着、タオル) をリュックに入れたか、使用したら洗濯機に入れているかを確認する、などの使い方もある。
三つ目は、不慮の事故の予防だ。埼玉県の小林節子さん(仮名、57歳)は、「青森に住む母が、『腰が痛い、腰が痛い』と電話で言っていたが様子がわからないため、『ちかく』で母の歩き方を見ると、右足の着地がおかしいことに気がついた。病院に行かせると『脊柱管狭窄症』と診断され、入院した」とのことだ。
電話どうしでの会話では見えなかった親の異変を具体的に確認でき、不慮の事故を防止できた例だ。
グループ通話機能でさらに広がる可能性
①複数の子供による親の見守り
従来モデルでは、親の在室状況や起床・就寝などの生活リズムの変化を把握できる見守りが、親と子供との1対1で可能だった。新モデルでは、こうした親の見守りが複数の子供でも可能となった。
この機能により、例えば長女が仕事で見守りができない時に、休暇中の次女が見守れるなど、不慮の事故のリスクが下がり、安心感が高まる。
②医療・介護従事者の負担軽減
医師・看護師やケアマネなどの医療・介護従事者が、高齢の親との日々の連絡・相談やモニタリングなどを、顔を見ながら行うことができる。これにより、医療・介護従事者の業務負担が軽減され、より迅速な対応が可能になるだろう。
従来モデルでも親宅を訪れたケアマネと娘が担当者会議に活用している例がある。最大4人まで同時に会話ができるので、利用者とその家族、多職種とのやりとりも可能だ。
③家族間コミュニケーションの活性化
本機能により、親を中心に複数の家族や親戚との⽇常的なコミュニケーションの頻度が高まりやすくなる。
これにより家族間(特に、親と子の縦の関係に加えて、叔父、叔母、兄弟姉妹など横の関係の拡張)のコミュニケーションが活性化するだろう。「ちかく」が掲げるデジタル近居サービスの中身がさらに深化したと言える。
こうした付加価値の高い機能の追加にも関わらず、利用に際しては、全てのユーザーに追加費用は発生しないとのことだ。
1月の米国CESで日本企業のエイジテックが注目された。だが、CESに未出展でも優れたエイジテックがわが国には沢山ある。「ちかく」はその代表だ。
テレビを活用した訪問看護のオンコール業務効率化の実証を開始
上記した医療・介護従事者の負担軽減の可能性に関連し、社会医療法人石川記念会HITO病院とNTTコミュニケーションズが、「ちかく」を活用した訪問看護のオンコール業務効率化に関する実証を2025年3月より開始することになった。
オンコールとは、訪問予定がない日や夜間などにも、利用者や家族からかかってくる緊急の電話に対応するために看護師が待機することをいう。オンコール体制があるおかげで、利用者やその家族はいつでも連絡できる安心感を得ることができる。
一方で、24時間365日のオンコール対応は看護師にとって負担が大きく、また、電話によるコミュニケーションでは患者の容態把握が難しいため訪問の優先順位がつけにくいのが現状だ。
今回の実証では、「ちかく」を活用し、訪問看護のオンコール業務をどこまで効率化できるかを検証するものだ。訪問看護の利用者と家族、看護職の双方にメリットのある使い方が期待される。