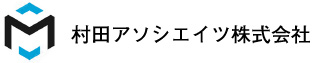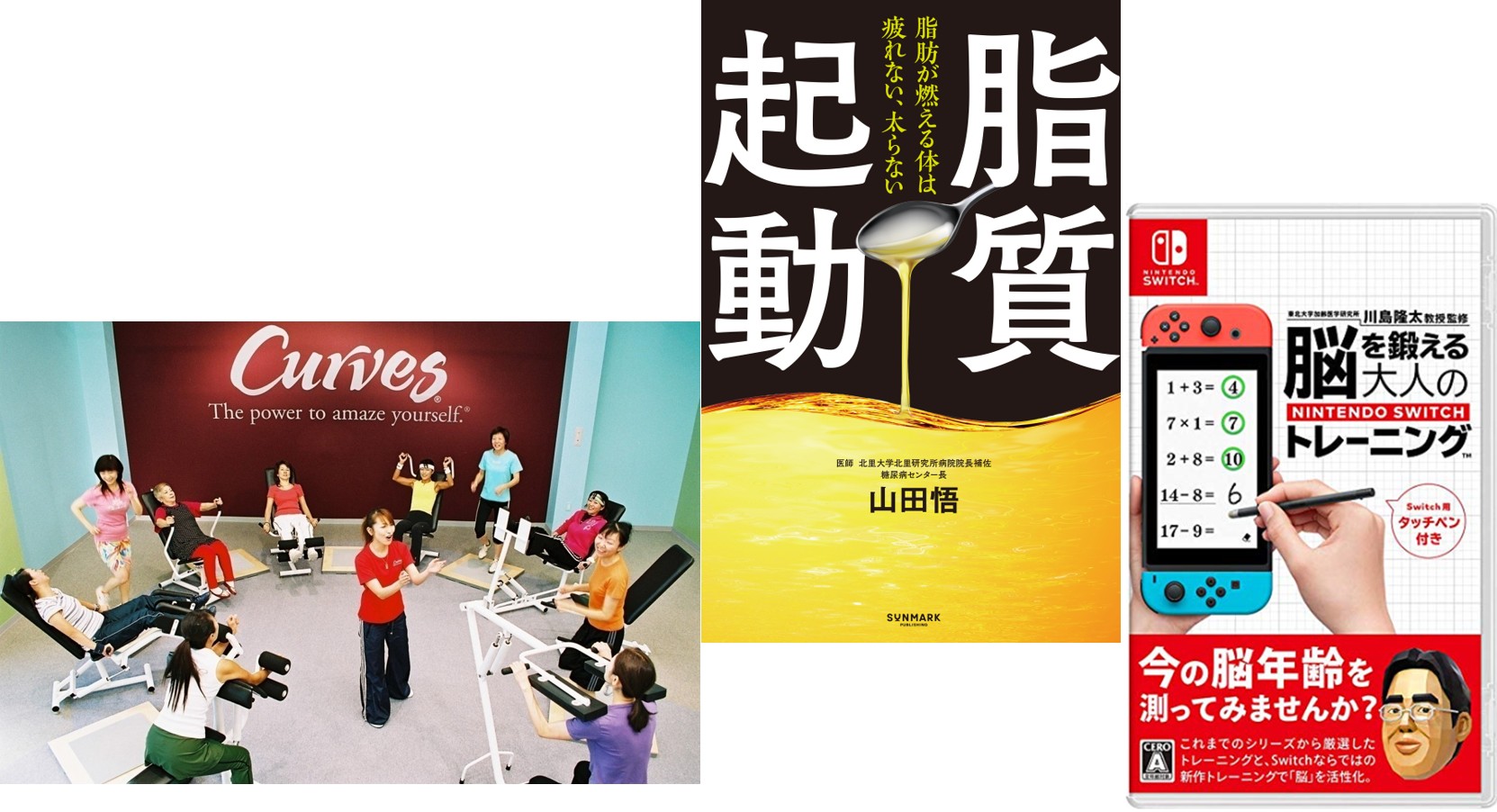高齢者住宅新聞連載 村田裕之の「シニアビジネス相談室」第99回
民間企業が自治体と同等のサービスをしていたら勝てない
地域のシニア向けに会員制事業を運営する企業から「事業収支が赤字で困っている」との相談を時々受けます。事業内容を尋ねると、ワークスペースや会議室のレンタル、タブレットのレンタルと講習、体操教室、カフェなどが多いです。
会費は月3千円(税別)程度でオプションサービスごとに追加料金が発生する形態が多く、会員数は数百人程度の場合が多いようです。数百人会員がいても月会費を払わない利用毎の都度払い会員が多いなどの例もよく見られます。
こうした事業の苦戦理由は、まず収入不足です。対象地域で自治体が同様のサービスを公民館などで低価格で提供しており、民間企業はそれ以上の価格にしづらいためです。
自治体が低価格でも提供できるのは、収入不足を自治体の予算(税金または補助金)で補填しているからです。
次に、サービス内容も価格も同じなら、自治体が行う方が信用も高く、利用者に選ばれやすいためです。つまり民間企業が自治体と同等のサービスをしていたのでは勝てません。
自治体と同じ土俵に立たず、「民」の強みで付加価値向上を
このような苦戦時の対策は、端的に言えば「自治体と同じ土俵に立たない」ことです。自治体では提供しないサービスを行うことで、自治体ではできない付加価値をつけることです。
例えば、自治体が運営するスポーツジムは結構ありますが、パーソナルトレーニング、食事指導、24時間営業を行うところはまずありません。
自治体は市民に広くあまねくサービスするのが役割なので、民間企業は「顧客毎にカスタマイズ」したきめ細かな対応が差異化になります。
地域のシニアの大きなニーズに移動手段の確保があります。運転免許を返納する人や自力での移動が難しい人が増えているためです。
海外では配車サービスが普及し、タクシーよりも割安に移動できますが、日本では法規制が厳しく、一部の地域以外普及していません。
シニアビジネスの基本は「不(不安、不満、不便)の解消」です。民間企業の強みを生かした不の解消に新たな事業機会があるはずです。