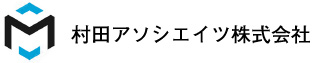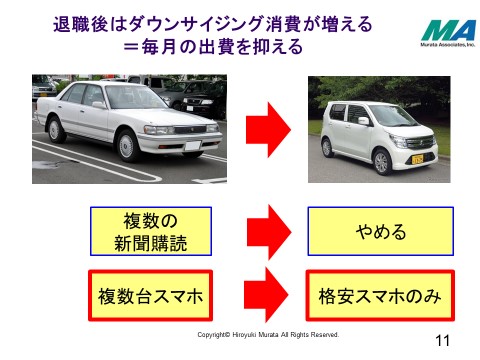高齢者住宅新聞連載 村田裕之の「シニアビジネス相談室」第11回
潜在ニーズのようで、ほとんど参考にならない無責任意見があふれるだけ
新商品開発や商品の発売前にグループインタビューの形で市場調査をすることも多いようです。しかし、私はこうした手法で消費者の本音が引き出されるとはまったく思えません。
その理由は、調査会社が選ぶグループインタビューの人たちは、本当の消費者あるいはターゲット顧客を代表している人たちではないからです。
グループインタビューへの参加者は、高額な謝礼を受け取るのに加えて、別室から調査会社のスタッフによりインタビューの様子をモニターされます。
参加者は、謝礼を払ってくれる調査会社に配慮して、本音を発言しなかったり、逆にあまり強く感じていないネガティブ意見をポーズとしてわざと発言したりします。
だから、本当の消費者やターゲット顧客としての意見にはならないのです。
また、インタビューを行う人は、意見を尋ねる時にできるだけ具体的に答えられるような質問を投げかける必要がありますが、これにはそれなりの力量が求められます。
単に「これについてどう思いますか?」といった抽象的な質問を尋ね、それに対して参加者が思いつくまま、あれだ、これだ、と言った意見は、ほとんど参考になりません。
そうした意見には具体的なニーズではなく、「ニーズっぽいけれど、実際には参考にならない多数の無責任な意見」があるだけです。
参加者に「当事者意識」をどれだけ高められるかがカギ
一方、読者参加型のおせち料理品評会のように、参加者が商品提供企業の企画スタッフの一部であるかのような雰囲気づくりをした時は、比較的良い意見が得られます。このやり方だと参加者に当事者意識が芽生え、真剣に意見を言うからです。
おせち料理の品評会では、まず目の前に料理が並びます。それを見たり、食べたりしながら出す意見なので、出てくる意見は極めて具体的で、参考になる情報となります。
総じてグループインタビューが効果を発揮するのは、食品であれば「おいしいか、まずいか」を聞く場合、他の商品であれば「買いたいか、買いたくないか」の白黒がはっきりした意見を聴取する時です。