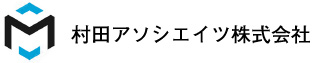不動産経済Focus & Research 知っていると便利 シニアビジネスの極意 第35回
シニア向け店舗を成功させる「5つのコツ」
筆者は時々、「シニア向け商品・サービスをひとまとめにした店舗は受けないか。そうした事例はないか」と質問を受ける。質問者の意図は、シニア向け商品・サービスがひとまとめにあれば、買い物の利便性が上がり、集客力も売り上げも上がるのではないか、ということだ。
結論から言うと、日本ではこうした店舗・モールで成功した事例はほとんどない。一方、これまでの苦戦事例に学び、「こうすれば失敗せず、成功確率が上がる」というコツはある。それは次の通りだ。
- 「シニア向け」を訴求しない。シニアが求める商品・サービスの「価値」を訴求する。
- 「コト消費」に重点を置き過ぎない。「モノ消費」とのバランスを取る。
- ノスタルジー消費をうまく活用する。ただし、対象とする商材はよく吟味する。
- 「あれもこれも」やらない。自社の強みに特化して商品・サービスの差異化を図る。
- シニア割引は来店効果あり。シニア向けに訴求してもよい例外。
以下に、各項目の詳細を解説する。
1.「シニア向け」を訴求しない。シニアが求める商品・サービスの「価値」を訴求する
かつて、大手スーパーのイオンが、シニアに代わる呼称として55歳以上の人を「グランド・ジェネレーション」と呼び、略称を「G.G世代」とし、かなり宣伝した。だが、肝心の対象者にあまり受けなかった。意味がよく伝わらなかったからだ。
日本橋にある三越本店や髙島屋日本橋店などは、昔からシニア層の来店割合が高いが、「シニア向け」などと謳うことは決してない。「シニア向け」という訴求が強いと、シニア以外の年齢層の客足が遠のくだけでなく、肝心のシニア層も来店しづらくなるからだ。
「シニア向け」と訴求する以前に、シニアが求める商品・サービスの「価値」を上げ、それを訴求する方がより重要だ。
2.「コト消費」に重点を置き過ぎない。「モノ消費」とのバランスを取る。
2014年頃、イオンは都内の葛西店を旗艦店舗にしようとしたが、かなり苦戦した。主な理由は、その頃小売業で話題になっていた「コト消費」に重点を置き過ぎた店舗づくりを行ったためだ。
数多くのカルチャープログラム、小型フィットネス、楽器演奏用防音ルームのレンタルなど、コト消費の割合がかなり大きかった。こうした商材は、販売効率が低く、大量のモノ消費に慣れていたスーパーの業態に合わなかった。
コト消費は、やり方によってモノ消費の促進剤になるが、両者のバランスと組み合わせ方に工夫が必要だ。
3.「あれもこれも」やらない。自社の強みに特化して商品・サービスの差異化を図る。
イオン葛西店は、いわゆる総合スーパーで、食料品や日用品のみならず、衣料や家電、家具等、日常生活で使う様々な商品を扱っていた。
店舗全体をシニア向けにしようと「あれもこれも」と取り組んだ。その結果、実験的な売り場が増え、取り組みが中途半端になり、売上は伸び悩んだ。
一方、昨年9月に埼玉県久喜市に開店した「ヤオコー久喜吉羽店」は、50代以上の「ミドル・シニア層特化型店舗」と位置づけている。
ヤオコーの強みは「食品スーパーに特化」していることだ。ヤオコーは生鮮食料品などの品質が高く、評判が良いことで知られている(図1)。彼らの強みである「高品質の食品」を軸にシニア向け商品の差異化を図っている。
4.ノスタルジー消費をうまく活用する。ただし、対象とする商材はよく吟味する。
ヤオコーの川野澄人社長によれば「久喜吉羽店では、ディープフライのようなベーシックな揚げ物、コッペパンや焼きそばパンなど、シニア層に支持される昔ながらの定番商品に磨きをかけた」とのことだ(図2)。

これは、私が提唱している「ノスタルジー消費」を狙ったものだ。主に40代以降に現れる消費形態で、50代以降の年齢層でも見られる。特定の世代が20歳頃までに共通に体験する文化体験(世代原体験)の影響が現れる消費行動だ。
ノスタルジー消費の特徴は「新しいもの」より「昔なじんだ安心なもの」を求める傾向が強いことだ。これに触れると昔の記憶と情動が一緒に呼び起こされ、若くて元気で幸せだった頃の自分を追体験できる。ターゲット層の子供の頃の食文化を追体験する商品に注力しているのが特徴だ。
5.シニア割引は来店効果あり。シニア向けに訴求してもよい例外。
映画館や劇場、小売業、理髪業などに見られる「シニア割引」は来店効果がある。小売業では例えば、イトーヨーカドーで60歳以上を対象に毎月15日、25日に5%割引が受けられる「シニアナナコカード」、あべのハルカス近鉄本店が65歳以上を対象に割引サービスを提供する「ハルカスシニアパスポート」などがある。
これらが許容されるのは経済的メリットを感じるからだ。シニア向けと言われるのは嫌だが、得だから割り切って使うのが本音だ。
以上の5つ以外にもシニア向け店舗を成功させるコツはあるが、少なくともこの5つを意識することで大きな失敗はしなくなるだろう。