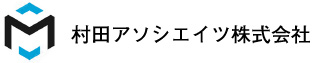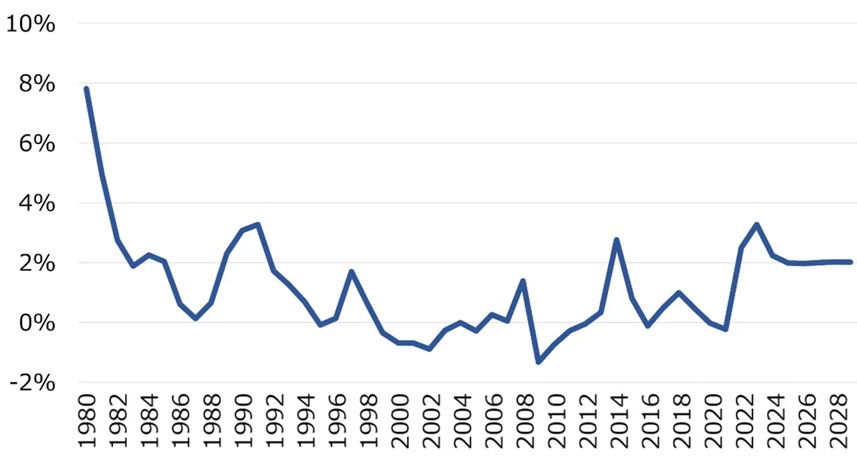シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第219回
以前は、それぞれ別の業態だったスーパー、コンビニ、ドラッグストアが、互いに似たような品揃えになり、境界が不鮮明になってきた。
このように、元々は違ったものが、互いに似てくることを「コンバージェンス(Convergence)」と言う。
コンビニの「スーパー化」の例:ローソンストア100
小売業におけるコンバージェンスの例は、コンビニの「スーパー化」だ。ローソンが始めた「ローソン100」がそのはしりだ。
この業態は、もともと100円均一ストアからスタートしたが、肉や野菜などの生鮮食料品が比較的豊富なことが売りになっていった。その後、「ローソンマート」を経て、現在は「ローソンストア100」となっている。
スーパーの「コンビニ化」の例:まいばすけっと
一方、別の例はスーパーの「コンビニ化」だ。2005年にイオンリテールが始めた「まいばすけっと」がそれだ。コンビニの跡地など、都市部の150平米ぐらいの空き店舗に展開する小型スーパーだ。
売っているものは、イオンのプライベートブランド(PB)商品や生鮮食料品が中心で価格の安さを売りにしている。
来店客は、都市部買い物難民の高齢者、遠出ができない子育て主婦、帰宅の遅いビジネスパーソンなどが中心だ。営業時間は、概ね朝7時から深夜0時までで、通常のスーパーの営業時間外の顧客の受け皿になっている。
ドラッグストアの「スーパー化」、コンビニの「ドラッグストア化」も
さらにドラッグストアの「スーパー化」も進んでいる。大手のウエルシア薬局はイオングループ傘下のため、イオンのPBを多数扱うほか、生鮮食品以外ではスーパー以上の価格競争力を持つ店舗も多い。
また、一部のローソンやファミリーマートには、薬局を併設している店舗もある。これはコンビニの「ドラッグストア化」だ。

出典:ローソンホームページ
コンバージェンスの進展で似た業態が互いに深化
異なる業態間でコンバージェンスが進む過程で、⑴互いに相手商品の機能を取り入れる(相互学習)、⑵商品の改善と選択が進む(淘汰)、⑶ほぼ同じような商品構成となる(統合)といった深化が起こる。
これらの結果、各々業態で①多機能化、②付加価値化、③低価格化が進む。すると、小売業以外の業種・業態にも影響を及ぼすようになる。その例を次に説明する。
競争力が下がる小規模な「門前薬局」
近年、大手ドラッグストアでは、店舗内に保険薬局を持ち、全国の医療機関の処方箋薬を調剤してくれる。支払いの際に、クレジットカードなどの電子決済にすると、例えばウエルシアの場合、WAONなどの支払いポイントが付与される。
さらに、薬を受け取った後に市販の薬や化粧品、日用品、食料品を比較的低価格で買うことができ、利便性が高い。
これに対して、医療機関最寄りの小規模な保険薬局(門前薬局)で処方箋薬を受け取る場合、支払いポイントは付与されない。
また調剤に時間がかかることが多い。散々待たされたうえ、窓口での説明が的外れだったり、接客スキルが未熟だったりすることが少なくない。
厚生労働省は「保険薬局は、ポイントなどの経済的付加価値の提供ではなく、懇切丁寧な説明の実施、服薬指導の質の向上などによって患者から選ばれるべき」という主旨の見解を示している。
だが、私が知る限り「懇切丁寧な説明」や「服薬指導の質」が的確にできている門前薬局は少ないようだ。
コンバージェンスが規制産業の質を向上する
この理由は、門前薬局の大半が最寄り医療機関べったりで、営業努力をしなくても客が来る構造になっているためだ。
このような「供給者視点」の門前薬局は、コンバージェンスによって多機能化・付加価値化したドラッグストアに比べると競争力がかなり下がる。
このため、ドラッグストアの利便性に気づいた人は、徐々にこうした門前薬局を利用しなくなるだろう。
小売業態間のコンバージェンスは、規制で守られて、旧態然とした産業に競争原理を導入し、当該産業全体の質の改善をもたらすことになるだろう。